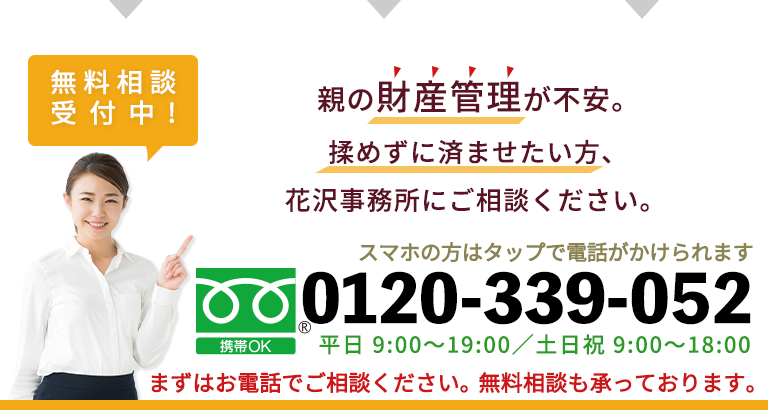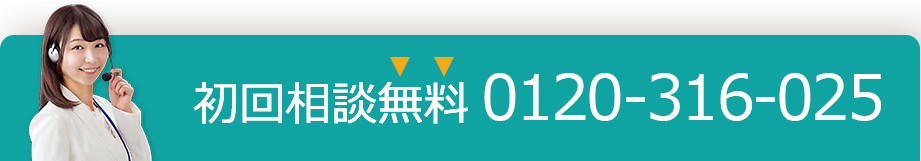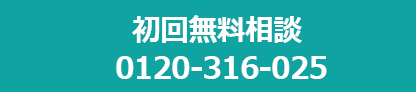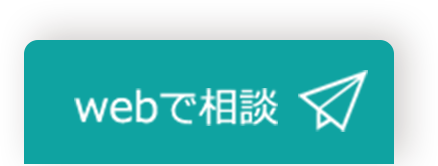遺言執行は、故人の遺志を実現する重要な手続きですが、複雑で専門的な知識が求められます。この記事では、遺言執行の流れや注意点、専門家への依頼方法などを解説し、スムーズな遺産承継を行うための情報をお伝えします。
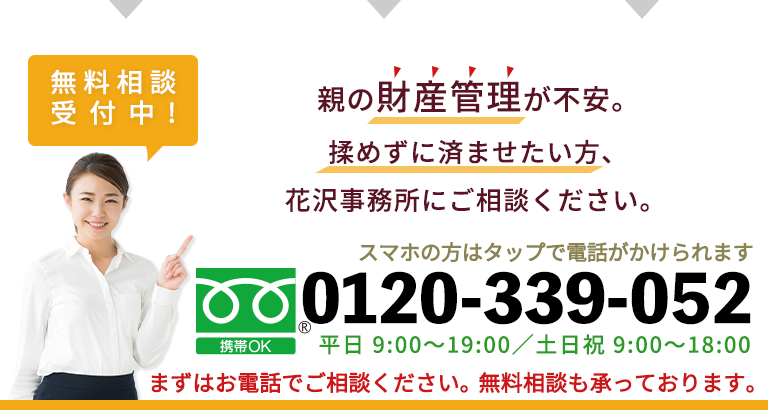
遺言執行とは
遺言執行とは「遺言の内容を実現させること」です。
具体的には、相続や遺贈による不動産の名義変更や、預貯金口座の相続による解約、相続人への振込手続きや遺言書で指定した公共団体等への寄付の実行などを行います。
遺言は、遺言を作成した人(遺言者)が亡くなった時点で効力が発生しますので、当然ながら、遺言者がご自身で遺言の内容を実現することはできません。そこで本人に代わり、遺言に伴う各種手続きを遺言執行者または法定相続人が行う必要があります。
遺言執行者の指定は、遺言書で指定しておくか、家庭裁判所に申し立てて選任する形で行います。遺言執行者の指定がない場合は、法定相続人が協力して遺言執行をすることになります。
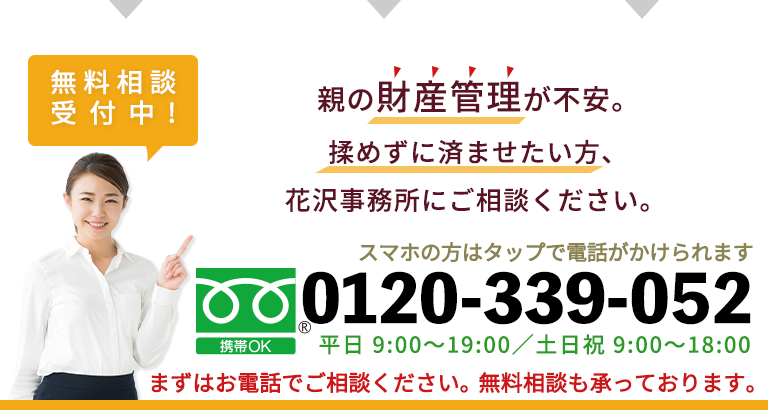
遺言執行で押さえておきたいポイント
1.遺言の内容を確認する
遺言が有効であることを確認するために、遺言の形式(自筆証書遺言、公正証書遺言など)や内容を精査する必要があります。特に自筆証書遺言では法律に従った形式で作成されていない場合、その内容が無効となることがあります。
2.遺言執行者を確認する
遺言執行者が指定されている場合、その人物が遺言執行を行います。遺言執行者がいない場合、法定相続人が協力して遺言執行をすることになります。裁判所に申し立てて遺言執行者を選任してもらうこともできます。
3.遺産を把握する
遺言に基づいて遺産を分ける前に、被相続人(遺言者)の所有していた財産をすべて把握する必要があります。これには不動産、預貯金、株式などが含まれます。相続人や他の関係者からの情報収集をすることも必要です。
4.相続人を確認する
遺言執行者は、遺言書に記載された相続人及び受遺者を確認し、相続の手続きを進めます。相続人及び受遺者が複数いる場合、遺産分割の手続きについても慎重に取り扱う必要があります。
5.債務の支払いをする
被相続人に未払いの債務がある場合、遺言書の内容によっては、その支払いも遺言執行者の役割の一部です。債務の返済を遺産から行う必要があります。
遺言執行にはさまざまな手続きが必要で、尚且つ慎重に行うべき手続きも多いため、できるだけ専門家に相談することをお勧めします。花沢事務所でも遺言執行のご相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
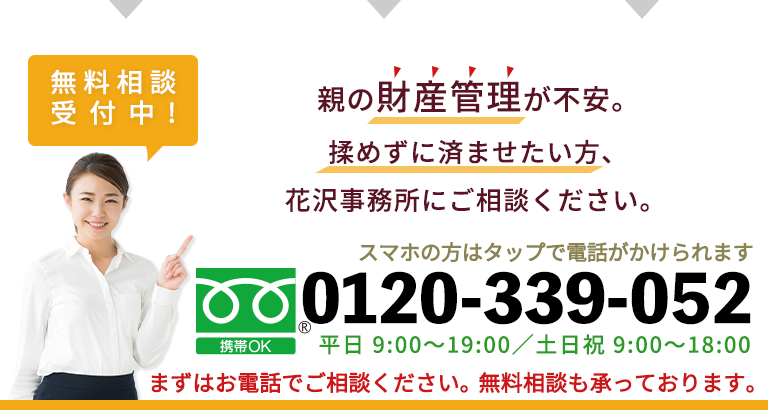
遺言執行の流れ/遺言執行者の役割
遺言執行者に任命された場合、相続財産の調査や相続人への通知、財産の分配など、多岐にわたる複雑な手続きを遂行する義務が生じます。以下では、遺言執行の流れに沿って、遺言執行者が担う役割とその責任範囲について詳しく解説します。
相続人の調査
遺言執行者は、遺言執行者に就任した旨や遺言書の内容などを法定相続人に通知しなければならない義務があるため、法定相続人が誰なのかを調べる必要があります。実際に誰が法定相続人になるのかは、被相続人の戸籍・除籍・原戸籍などを取得して、調査・確定します。具体的には、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本か除籍謄本から遡って、出生当時の戸籍謄本までつながるように取り寄せます。
相続人であることの証明とともに、他に相続人がいないかの確認も行います。亡くなられた方にお子様がいれば、その方々の戸籍謄本を取得します。お子様がいなければ、亡くなられた方のご両親の戸籍を、ご両親もお亡くなりになられていれば、亡くなられた方のご兄弟が法定相続人となります。他にご兄弟がいないかを確認するために、ご両親を出生まで遡って戸籍等を取得する必要があります。
被相続人の死亡の記載のある住民票除票または戸籍の附票とともに、法定相続人にあたる方の住民票または戸籍の附票を取り寄せます。
亡くなられた方の親族関係によって取得する戸籍等が異なるほか、取得する戸籍の数も多くなる場合もあるため、専門家に相談したほうがスムーズです。
遺言内容の通知
遺言執行者は、遺言執行をするにあたり、民法1007条により、遅滞なく、遺言執行者に就任した旨並びに遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
就任の通知とともに遺言書のコピーを同封して通知する方法が一般的です。
改正前の民法では、遺言の内容を相続人に通知すべき旨の明文規定はありませんでしたが、遺言執行者からの通知がない場合に、後から事情を知った相続財産を取得しない相続人との間でトラブルが発生することもあったため、遺言の内容の通知義務が明文化されました。
なお、遺言書に相続人ではないものに遺贈するというような場合では、特段、その受贈者に対しては、通知の義務がないものとされています。ただし、「包括受遺者」は民法990条により相続人と同一の権利義務を有すると規定されていますので、包括受遺者に対しては、通知をする必要があると考えられています。
相続財産の調査、相続財産目録の作成
遺言執行者は、遺言者の相続財産を調査し、相続人・包括受遺者へ相続財産目録を交付する義務があります(民法1011条1項、990条)。民法上、「遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない」と定められていることから、遺言執行者は就任後速やかに相続財産の調査・目録の作成に着手する必要があります。
不動産については、まず固定資産税の納税通知書を確認します。土地の地番や建物の家屋番号とともに固定資産税評価額が記載されているので、その情報を財産目録に記載します。ただし、納付すべき税額が発生しない場合(道路部分や山林など)は納税通知書に記載されません。共有不動産については、共有者を代表する1名にしか納付書が届かないため、そういった場合は、不動産所在地の市区町村から名寄帳を取り寄せて確認する必要があります。
金融資産や有価証券については、通帳を確認したり、各金融機関・証券会社・信託会社から残高証明書を取り寄せる等、遺言者が有していた財産の内容に応じた方法で調査をする必要があります。
なお、ネット銀行、ネット証券など、通帳や郵送物がない金融機関もあるため、取引があった可能性が少しでもある金融機関には、残高証明書の取得を依頼した方がよいでしょう。
続割合の指定・分配
遺言書では、相続人が受け継ぐ財産の割合(分数やパーセンテージ)を指定する方法と、第三者に相続分の割合を決めることを委託する指定方法があります。
遺言執行者は、遺言書に指定された相続割合に従い、遺産を分配する義務があります。法定相続分を超えて、相続財産の割合の指定があった場合でも、遺言執行者は、遺言書の通りに分配を執行すればよいとされています。
清算型包括遺贈の場合(不動産を売却して、売却代金を分割するといった場合)は、遺言執行者が財産を換価して、遺言書に指定された割合に従い分配をすることとなります。
相続財産の不法占有者への明け渡し・移転請求
遺言執行者が遺言の内容を実現する過程で、相続財産が第三者によって不法占有されている場合、遺言執行者はその占有を排除し、遺言内容を実現するため、不法占有者に対して相続財産の返還や明渡しを請求する権限を有します。
ただし、不法占有者が請求に応じず、訴訟を提起せざるを得ない場合、判例では遺言に相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載等がない限り、遺言執行者からの訴訟の提起は認めておらず、その財産の受益相続人が不法占有者に対して訴訟の提起を行うことになります。
財産の引渡し
遺言執行者は、遺言執行に関する事務を処理するにあたり、受け取った金銭その他の物、又は収受した果実及び相続人のために遺言執行者の名で取得した権利を遺言の趣旨に従って、相続人に引き渡し、又は移転する義務があります(民法1012条3項、646条)。
相続人から受け取った物、第三者から受け取った物でも、遺言執行者が遺言執行に関し保管している全ての物が対象となります。
また、この引渡義務は期限の定めがない債務と考えられるため、相続人等から催告があった時から遅滞の責任を負うとされます。
遺言執行者が義務を怠った場合、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の解任を申し立てる可能性があります。そのため、遺言執行者は遅滞なく財産を引き渡すことが重要となります。
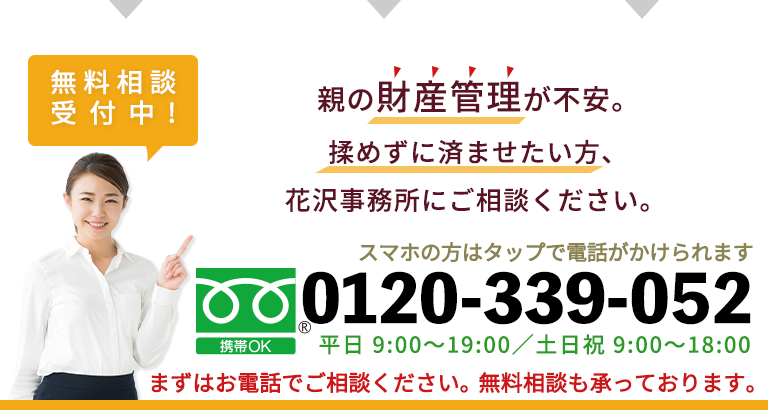
遺言執行を進める際に注意すべきこと
現行の民法上、遺言執行者には下記を含むさまざまな義務が定められています。
- 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
- 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
- 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
民法上の義務に違反がある場合、利害関係人からその責任を追及されたり、トラブルに発展する可能性があります。
遺言執行を行う場合、一般的な相続(遺産分割協議や法定相続分による相続)の手続と異なり特に注意しなくてはならないのは、遺留分侵害額請求への対応です。
遺言書の内容から、遺留分を下回る割合しか相続できない(何も相続しない場合も含む)方が居る場合、その方から遺留分侵害額請求がされる場合があります。
2019年6月30日以前に発生した相続の場合、遺留分を侵害する遺贈の効力が失われ、対象財産を遺留分権利者に帰属させるという方法が取られていたため、遺言執行者は、一旦、遺言の執行を中止するなどの対応が必要でした。
しかし、2019年7月1日の法改正により、遺留分侵害額請求があった場合でも、遺贈等の効力に影響することはなく、金銭を支払って解決すればよいということになりましたので、遺言通りの遺言執行を継続することができます。
また、相続税が発生して、更に困難な遺言執行が必要となる場合などもあり、遺言執行は複雑な法的・実務的手続きが伴うため、専門家のサポートを受けたほうがスムーズに進むことが多いです。花沢事務所でも遺言執行のご相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
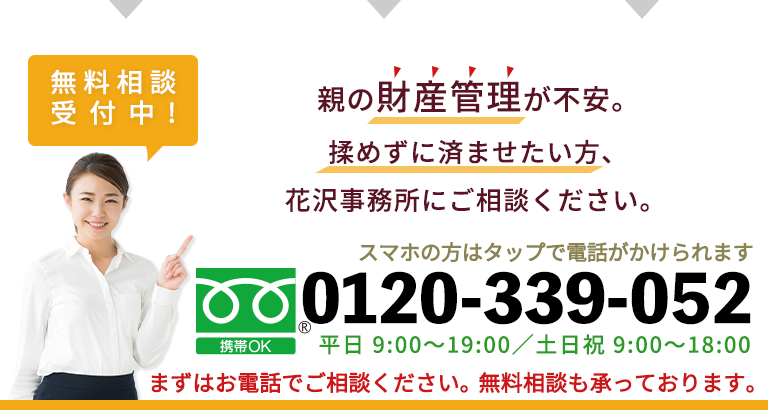
遺言執行者には誰がなる?遺言執行者の選任方法
遺言執行者の選任方法は、「遺言書に記載して指定する」「家庭裁判所に申し立てて選任してもらう」「遺言書の中で『遺言執行者を決める人』を指定し、その人が遺言執行者を決める」という3つの方法があります。
一般的には、遺言書に記載して遺言執行者を指定する方法が多く、指定された方が執行業務をすることが大変な場合は、司法書士等の専門家に遺言執行業務の代理を依頼することも可能です。
遺言書に遺言執行者の指定や遺言執行者を決める人の指定がない場合は、受遺者が手続を進めるか、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をする必要があります。
遺言執行者を解任または辞任する方法
遺言執行者がその任務を怠ったとき、その他解任するにあたり正当な事由があるときは、利害関係人の請求により家庭裁判所から解任されることがあります(民法1019条①)。
「任務を怠ったとき」とは、遺言執行者が遺言執行の任務に違反した行為をしたり、任務を放置することなどが考えられます。
「その他正当な事由」とは、遺言執行者が長期の病気になった場合や行方不明になった場合などのほか、遺言執行者が相続人の一人に特に有利な取扱いをして公正な遺言執行が期待できないことなどが挙げられます。
具体的な解任の手続きとして、相続人や受遺者、その他利害関係人から遺言執行者に対して家庭裁判所に解任を請求する必要があります。
また、遺言執行者の辞任は、「正当な事由」がない限り、遺言執行者自身が自由にすることはできないとされ、こちらも家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
「正当な事由」とは、例えば、遺言執行者が長期の病気や遠方に転勤になった場合などにより遺言執行が困難な状況になったことが考えられます。
なお、遺言により遺言執行者に指定された際に、就任の意思表示をせず「辞退」することは家庭裁判所の関与は必要なく自由にできますが、就任した場合には、自由に辞任できなくなります。
遺言執行者がいない場合はどうしたらいい?
遺言書に遺言執行者の指定がない(遺言執行者がいない)場合であっても、受遺者の方が遺言の内容に基づいて預貯金解約や相続登記等の相続手続を行うことは原則として可能です。ただし、金融機関によっては遺言により預貯金解約を行う際に遺言執行者をたてることを求められる場合があります。
また、遺言の内容に相続人の廃除や認知についての条項があるときなど、遺言執行者を選任した上で裁判所や市区町村に対する手続きが求められる場合があります。
遺言執行者が必要となった場合、管轄の家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることになります。その場合はまず弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
花沢事務所でも遺言執行のご相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
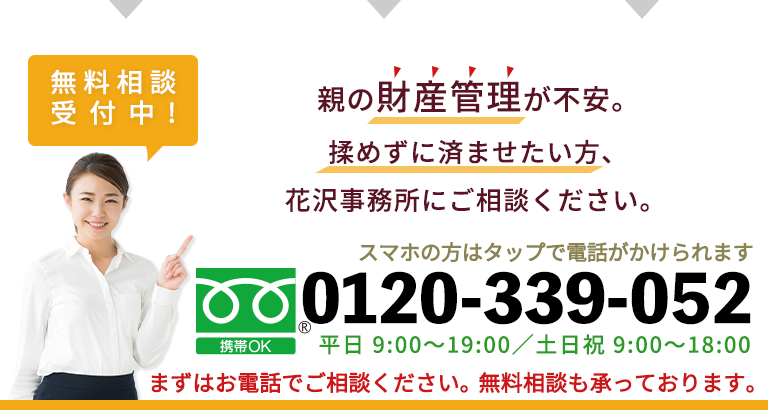
遺言書や遺言執行でよくあるトラブルと回避方法
遺言内容が不明確でよくわからない
遺言の内容があいまいで何を意味しているのか分からない場合や、実現できない内容になっている場合、その部分の遺言は無効になることがあります。しかし、遺言の解釈が分かれる場合や、遺言者の意図がはっきりしない場合は、遺言執行者ができる限り遺言者の意思を探る必要があります。
遺言の内容を解釈するにはどうしたらいい?
遺言を解釈するときには、次のようなことを考慮します。
- 遺言書全体の内容(前後の文脈を確認)
- 遺言を書いたときの状況(遺言者の家族関係や財産状況など)
- 遺言者の意図が分かる資料がないか
もし遺言の内容がはっきりせず、そのままでは手続きを進められない場合、遺言の文言と実際の処理に多少の違いがあっても、遺言の趣旨を変えない範囲であれば、遺言執行者が解釈を示し、関係者全員の合意によって対応できることがあります。
不動産の記載には特に注意が必要!
遺言の中で不動産の書き方があいまいだと、どの土地や建物を指しているのか分からず、法務局で名義変更の手続きができなくなる可能性があります。名義変更手続きができなくなると遺産分けもスムーズに進まなくなるため、そういった場合には専門家に相談することをお勧めします。
遺言内容が相続人の考えと相反する
遺言は亡くなった方(被相続人)の最後の意思を示す大切なものです。しかし、その内容が相続人全員にとって必ずしも納得できるものとは限りません。
たとえば、「自宅を特定の相続人に相続させる」といった遺言があっても、相続人全員で協議した結果、売却して現金を分け合ったほうが望ましいと判断されることがあります。また、「長男にすべての財産を相続させる」と記された遺言がある場合、他の兄弟が何も受け取れないことから、トラブルに発展するのを避けたいと考えるケースもあります。
このように、遺言の内容が相続人の意向と異なる場合でも、相続人全員の合意があれば「遺言と異なる遺産分割」が認められるケースがあります。
遺言と異なる遺産分割をするための条件
遺言を無視して自由に遺産を分けることはできませんが、次の4つの条件を満たせば、遺言と異なる方法で分割することが可能となります。
- 遺言で「遺産分割の禁止」がされていない
遺言書に「この内容以外で遺産を分けることを禁じる」という記載がある場合、禁止された期間で変更することはできません。 - 法定相続人全員の合意が取れている
相続人の誰か一人でも反対がある場合、遺言と異なる分割はできません。全員が納得し同意することが必要です。 - 遺言執行者の同意が取れている
遺言執行者が指定されている場合、その方の同意も必要です。遺言執行者は、被相続人の意思を実行する役割があるため、遺産の分け方に関与します。 - 相続人以外の受遺者の同意が取れている
遺言で相続人以外(たとえば親族以外の友人や団体)に財産を渡すとされている場合、その方の同意も必要です。
遺言の内容に不満があっても、全員が合意すれば遺言と異なる分け方が可能です。ただし勝手に変更することはできず、遺産分割協議書を作成し、正式な手続きを踏むことが大切です。「遺言があるから変えられない」と思い込まず、全員の意見を尊重しながら、最適な遺産分割を考えることが大切です。
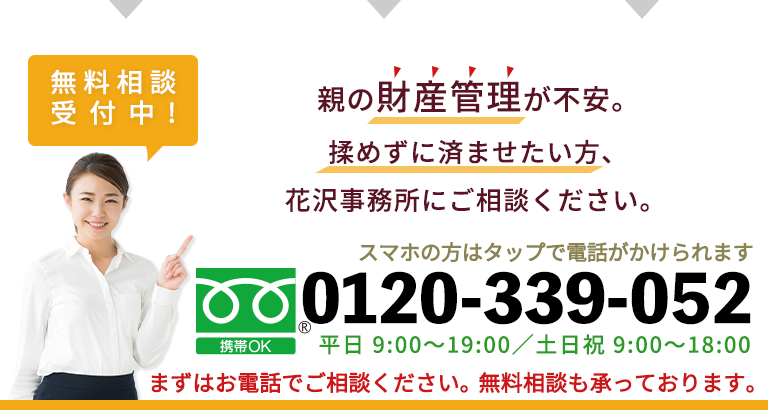
相続人と顔を合わせたくない
亡くなられた方が遺言書を作成していなければ、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、遺産の分け方を決める必要があります。そのため相続人同士が直接集まり、話し合いをしなければなりません。
遺言書を作成しておけば、遺言の内容に沿って手続きを進めるだけで済むため、相続人同士が直接やり取りをする機会を大幅に減らすことができます。
相続人同士で直接やり取りをしたくない場合、遺言作成時に専門家などの第三者を遺言執行者に指定しておくことで、相続人同士がやり取りをすることなく、遺言執行者を通して遺言の内容を実現することが可能です。
また、相続人の1人が遺言執行者になっている場合でも、専門家に遺言執行を依頼することで、相続人同士での直接連絡はせずに手続きを進めることができます。
遺言執行者が病気や怪我で動けない
遺言執行者が病気や怪我で動けない場合、遺言執行者は、第三者に遺言執行の全部または一部を委任することができます。これを「復任権」といいます。
ただし、2019(令和元)年7月1日より前に作成された遺言書では、原則としてやむを得ない事情がなければ委任できません。たとえば、病気や入院、認知機能の低下等により手続きが難しい場合などが該当します。ただし、2019年7月1日以前の遺言であっても、遺言書に「第三者に遺言執行を委任できる」旨が明記されている場合は、委任が可能です。
遺言執行を委任する場合は、司法書士、行政書士、弁護士などの法律の専門家に依頼するのが一般的です。
遺言執行者の資質に問題がある
遺言執行者が業務を行わない、または不適切な行動をしている場合、家庭裁判所に解任を申し立てることができます。
遺言執行者を解任できるのは「遺言執行者がその任務を怠ったとき、その他正当な事由があるとき」とされ(民法1009条)、具体的なケースとしては下記のような場合が考えられます。
- 遺言執行が進まない、遅すぎる
- 連絡が取れない
- 財産を不当に処分した
- 相続財産を着服した
- 相続人に不利益を与えた
ただし解任の申立てには時間と費用がかかるため、問題の影響を慎重に評価し、解任が必要かどうかを判断することが重要です。
このように遺言執行者に関する問題はトラブルが複雑化しやすいため、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。花沢事務所でも遺言執行のご相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
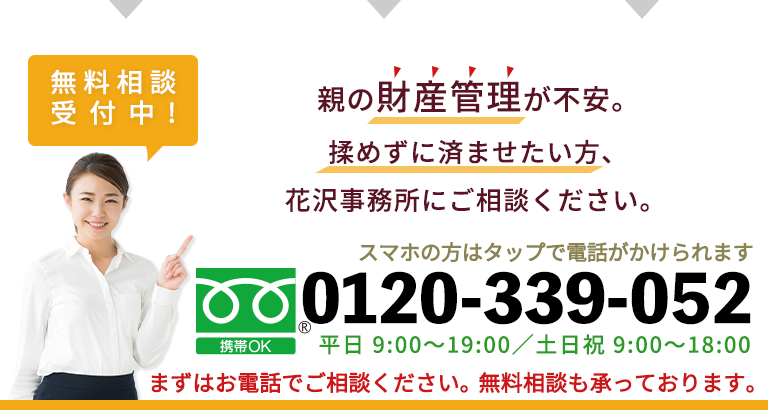
司法書士に遺言執行を依頼する
遺言執行における司法書士の役割
遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ誰でもなることができます。そのため、相続人や受遺者(財産を受け取る人)が指定されることも少なくありません。
しかし、遺言執行には 相続手続き・財産管理・名義変更 など、法律や実務の知識が必要な場面が多く、不慣れなまま進めると、相続人同士のトラブルにつながるリスクもあります。
そこで司法書士に遺言執行を依頼することで、手続きのサポートを受けられるとともに、トラブルを未然に防ぐことができます。
遺言執行を司法書士に依頼するメリット
司法書士は、法律事務の専門家として遺言執行をスムーズに進める役割を担います。
司法書士を遺言執行者に指定することで、以下のようなメリットがあります。
- 相続手続きの負担を軽減できる
- 法的なミスやトラブルを未然に防げる
- 不動産の名義変更なども一括で対応できる
そのため、ご遺族は煩雑な手続きを気にせず、故人を偲ぶ時間を過ごすことができます。また、相続手続きがスムーズに進むことで、遺産を早く受け取ることができるのも大きなメリットです。
遺言書の作成支援も司法書士への依頼がおすすめ
遺言書は、法的要件を満たしていないと無効になることがあります。特に自筆証書遺言は要件が厳しく、不備があるとせっかく作成しても無効になってしまう可能性があります。
公正証書遺言の場合、公証役場とのやりとりや必要書類の準備が必要ですが、これらを専門家が代行することで遺言者の負担を軽減できます。また公証人は遺言の希望通りに作成してくれますが、「この書き方ではトラブルになる可能性がある」というようなアドバイスはしてくれません。
そこで専門家である司法書士に依頼することで、遺言者の意向を汲み、法的に有効であることはもちろん相続トラブルを防ぐためのアドバイスをもらうこともできます。
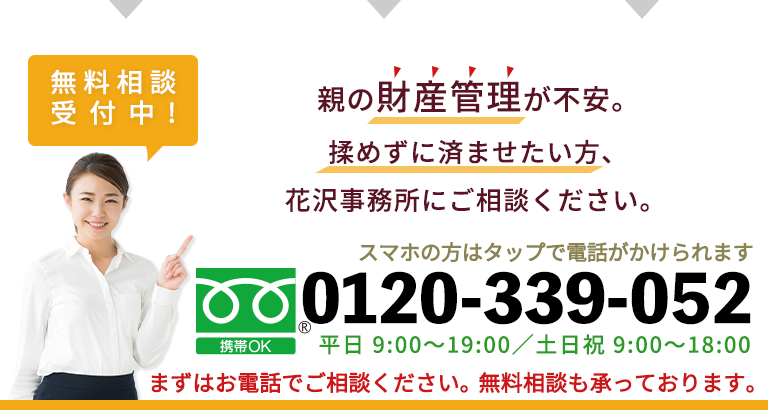
まとめ
遺言執行者は「相続人を調べて通知する」義務を担う
遺言執行者には「法定相続人に遺言の内容を通知する義務」があります。つまり、誰が相続人なのかを正確に調べて、伝えなければならないのです。
しかし、相続人を調べるのは大変な作業です。
相続人を確定するために、被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から死亡まで遡って取得し、関係を確認する必要があります。
相続人の調査が大変な理由
- 相続人全員を見落とさずに特定する必要がある
- 戸籍が複数に分かれていて、1通では済まない
- 兄弟姉妹が相続人になる場合、さらに親の戸籍まで確認が必要
- 古い戸籍は読みにくく、複雑なケースもある
もし調査を間違えた場合、相続人への通知漏れが発生し、後々トラブルになる可能性もあります。
遺言執行者は非常に重要な役割を担っているため、相続人調査に不安がある場合は専門家に相談することをお勧めします。
花沢事務所では遺言執行の実績も多数ございます。お電話やメールでのご相談もお受けしていますので、遺言執行に関するお悩みやご不安がある方はお気軽にお問い合わせください。