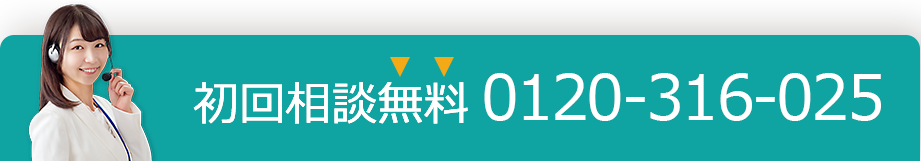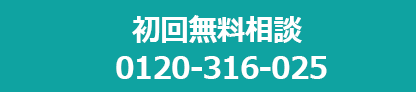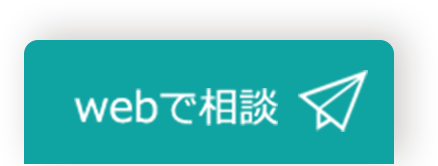遺言書作成は、司法書士法人花沢事務所にご相談ください
あなたの財産が争いの火種になることを防ぐ遺言書の作り方
相続には少なからずいざこざが生まれます。一生懸命働いて、築き上げてきたあなたの財産が争いの種にならないようにするために・・・遺言はその最善の方法です。長い間、人生を共にしてきた人への最後の仕事です。せっかくの遺言が無効にならないように、法的要件が求められます。
遺言書の作成/内容の決まり
遺言を書くには一定のルールがあり、そのルールに従って遺言書を作成しなければなりません。ルールが守られていない遺言書は無効になってしまいます。またルールはしっかり守られていても内容が曖昧であったり、色々な意味に解釈できてしまう場合には争いの原因になることがあります。
遺言というと「縁起でもない」「暗い感じがする」といったイメージを持たれる方もいるかもしれません。しかし、遺言書がなく、相続人同士が争いになったり、親族の関係が悪化したりというケースは数多くあります。
家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の争いの3分の2は遺言を書いておけば防げたものであると言われています。遺言書を書くというのは、財産を持つ者の義務といっても過言ではありません。
遺言書には3つの種類があります。
1.自筆証書遺言
本人が遺言書を作成します。遺言の内容・日付・氏名を書き、押印します。
この場合、遺言書の内容は全文を自署することが必要です。ただし、財産目録についてはワープロ等で作成することができます。遺言書が複数ある場合には最も日付が新しいものが優先されます。
証人の必要はありません。遺言を秘密にできるというメリットはありますが、紛失や偽造の危険性があります。
自分自身で作成すれば、費用はかかりませんが方式不備等により無効になってしまう可能性はあります。
原則として検認手続きが必要ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用により法務局で保管されていた場合、検認手続きは不要です。
2.公正証書遺言
本人が口述し、公証人が筆記します。印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本が必要になります。自筆証書遺言と違い、偽造される危険性は極めて少なく、証拠能力も高いですが、作成手続きが煩雑になりやすい・遺言を秘密にできない・費用がかかる等のデメリットがあります。
また証人は2人以上の立会いが必要となります。検認手続きは不要です。
3.秘密証書遺言
本人が作成した遺言書に署名捺印をして遺言書を封じます。その際に、遺言書に使用したものと同じ印で封印をします。そして、公証人にこの遺言書は遺言者のものであるという確認を封筒に署名してもらう方法です。
遺言書の存在が明確であり、偽造の危険性は極めて低くなります。また遺言の内容も秘密にすることができます。
デメリットとしては作成の手続きが煩雑になりやすいことや費用がかかってしまうことが挙げられます。
遺言書で実現できること
遺言書では実現できる事柄は決まっており、その内容は大きく分けて3つあります。
① 遺贈に関する事柄
相続人以外または特定の相続人に特定の相続財産を相続させる。
遺言内容を実現するための遺言執行者の指定。
② 相続に関する事柄
法定存続分と異なる相続分の指定
不適切な相続人の廃除、または相続廃除の取消
5年以内の遺産分割の禁止
③ 身分に関する事柄
子の認知
未成年者の後見人等の指定
遺贈とは
遺贈とは、遺言によりもらう人(受遺者)の意思に関係なく財産の全部または一部を譲渡することをいいます。 遺贈には、財産の全部または一部を譲り渡す包括遺贈と、ある特定の財産を譲り渡す特定遺贈があります。
包括遺贈
包括遺贈とは、財産を特定して受遺者に与えるのではなく、全相続財産の5割とか全相続財産の4分の1のように、割合で相続財産を譲渡することです。 包括受遺者は相続人ではありませんが、民法上「相続人と同一の権利義務を有す」とされているので、プラスの財産だけではなく、債務も引き継ぐことになります。 債務の方が多い場合は、遺贈の放棄をすることができます。 遺言者が死亡したこと、自分に対して遺贈があったことを知ってから3ヶ月以内に放棄の申述を家庭裁判所に対して申し立てなければなりません。 放って置くと単純承認したものと見なされます。
特定遺贈
特定遺贈の場合、放棄に関する期限は定められていませんので、遺贈を放棄するも承認するも自由です。 ただし、受遺者が長期間にわたり放棄も承認もせずにいると、遺贈義務者であるその他の相続人が不安定な立場となります。 それを防ぐために、相続人やその他の利害関係者は、定めた期間内に遺贈の承認または放棄すべき旨を受遺者に対して催告することができます。 また、負担付遺贈というものもあります。 こちらは、遺贈するに当たり受遺者に一定の義務を課すことを条件に財産を与えるというものです。 例えば、「母親の介護をすることを条件に長男に自宅を相続させる」などです。 その他にも、停止条件付き、解除条件付きの遺贈などもあります。 詳しくはお問合せください。
遺贈の効用
遺贈は、必ず遺言によってなされるため、遺言書の作成が必要です。 特に内縁の妻に財産を遺す場合や法定相続分よりも多く与えたい場合などには、遺言書を作成しておくことで、あなたの意思を反映することが可能です。 遺された妻や子供たち、その他面倒を見てくれた方たちへの心配を少しでも緩和させることができるのではないでしょうか。
遺言書に関する相談事例
入院中の遺言書作成
ご依頼背景
Bさんから、「夫Aさんが遺言を書きたがっているが、脳梗塞で倒れており、自筆で書くことはできない。意識ははっきりしているものの、体力的には限界が近そうだ」とのご相談を受けました。
花沢事務所の対応内容
自分で手書きをする遺言(自筆証書遺言)が難しいことから、公証人の立ち会いのもとに作成する遺言(公正証書遺言)の作成を提案しました。当事務所は、Aさんへの聞き取りによる遺言原案の作成、戸籍謄本など必要書類の収集、公証人との連絡と当事務所の者2名が証人を担当しました。最終的に、病院へ公証人と証人となる当事務所の所員2名とともにお伺いし、無事に公正証書遺言の作成を完了しました。