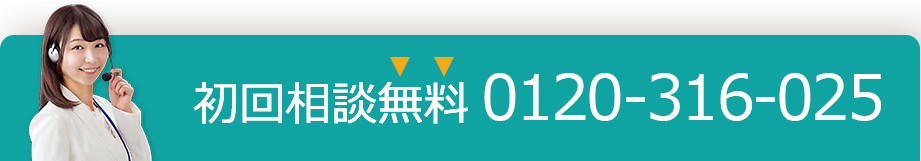両親のうち、財産・金銭管理をしていた親が先に亡くなってしまった場合や認知症になってしまった場合、あるいは施設に入所することになった場合など、子どもが親の財産を管理することになるケースは少なくありません。
しかし、どんなに誠実に管理していたとしても、いざ相続が始まったら、そのことが他の兄弟と揉める原因になることもあります。
望まぬ揉めごとに陥らないために、万が一、親の財産を管理することになった場合は、どうしたら揉めずに相続手続きを進められるか、注意点を知っておきましょう。
故人の預金管理をする際に確認しておくべきこと
相続税の申告をする際に、税理士が最も気を使うのは「預金残高」です。
一般的には、相続開始時点での預金残高で計算すれば良いため、故人の通帳や残高証明を確認すればいいのですが、一方で望まない揉めごとを予め防ぐために、以下のケースに当てはまる場合に税理士は厳重に確認を行います。
① 生前に頻繁に引き出しが行われていた場合
この場合、引き出した金額が贈与されている可能性、またはタンス預金など、「相続税を少なくするために財産を隠したかもしれない」という疑念を持たれることが多く、確認・調査が入る場合があります。
② 亡くなる2〜3日前にまとまった金額が引き出されていた場合
相続が開始されると、故人の銀行口座は凍結され、預金が引き出せなくなります。
そのため、入院費用や葬儀費用の支払いに当てるお金は、通常亡くなる2〜3日前に引き出すことが少なくありません。これは相続税を少なくするためではなく、入院費用や葬儀費用の支払いに当てるためなので、引き出し額を現金として処理します。
③ 2〜3年前から頻繁に一定額を引き出している場合
生活費レベルの金額なら問題はありませんが、それを超えると思われる金額については、税務署が使途不明金として「贈与」か「隠し財産」ではないかと疑います。
故人が使っていたとすれば、亡くなっているため確認しようがないですが、故人が亡くなる直前に寝たきり状態だった場合は、その財産を管理していた人に確認します。
ただし、引き出しに不自然な点があれば財産管理者が疑われますが、その財産がどこへ行ったのかが確定しなければ、税務署は課税することができません。そのため、不明のまま課税されないケースも少なくないようです。

親の代わりに親の財産(預金など)管理することになったら
親の財産を代わりに管理することになった「理由」にもよりますが、子どもが複数おり、そのうちの1人が管理をする場合、管理をしていない子ども(兄弟)から「親の金を着服しているのではないか?」と思わぬ疑惑をかけられたり、親が亡くなった後、遺産分割の際に兄弟間でもめる原因となることがあります。
そのような事態にならないために、管理者になった相続人は、以下のことに注意しましょう。
① 「親の財産はあくまで親の財産」であることを意識しておく
いずれは相続で引き継がれることになりますが、まだ自分の財産ではありません。自分の財産とはっきりと区別して、「親のためにどう使うべきか」を意識して管理をしていく必要があります。
② 管理内容を明らかにしておく
財産管理契約や任意後見契約、家族信託などの制度を利用して、管理内容を明らかにしておくことも大切です。家計簿をつけるなどして証拠を遺しておくことも有効でしょう。
また、親と1対1でお金のやり取りをすることは思わぬトラブルに繋がります。必ず別の相続人や関係者がいるときにやり取りするなど、「当事者のみが事実を知る」ということのないよう、備えておくことが重要です。
特に任意後見契約や家族信託などは第三者が関わることが多いため、客観的に管理内容をチェックすることもできます。親族間でのもめごとの火種を少なくすることができるので、上手く活用しましょう。
親の財産管理に使える制度
① 財産管理契約
高齢の方で身体の自由がきかなくなってきた場合や、高齢者向け住宅などに入居する際に、個別の任意契約を信頼できる第三者と結ぶ、財産の管理を依頼する契約です。
財産管理契約のメリット
自分の代わりに財産の管理を行う人を自由に決めることができます。
成年後見制度や任意後見制度と大きく異なるのは、契約の締結後、直ちに効力が発揮されるところにあります。
また、成年後見契約や任意後見契約は、契約者の意思能力の低下が条件となりますが、財産管理契約は民法の委任契約に基づく契約のため、「施設への入所を希望しているが、委任者の判断能力(意思能力)がハッキリしている場合」などに適用されます。
② 任意後見契約
委任者が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
任意後見契約のメリット
自分の代わりに財産の管理を行う人を自由に決めることができます。
任意後見契約のデメリット
本人の判断能力が衰えたときからしか効力が発揮されません。契約締結には、家庭裁判所への申立が必要です。
任意後見人になることを引き受けた「任意後見受任者」や親族が、家庭裁判所に対して「本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたので、任意後見人を監督すべき『任意後見監督人』を選任してほしい」旨の申立てを行い、受理された後より効力発揮となります。
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから、任意後見受任者は、「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することができます。
③ 家族信託
委託者となる人と受託者となる人同士が契約書を交わして、家族信託について取り決めます。
家族信託のメリット
本人が元気なうちから子どもに財産管理を託せるだけでなく、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、本人の意思確認手続きが本人に対して行われないため、実質的に資産凍結されることなく、財産管理の担い手「受託者」主導で、財産の管理や処分をスムーズに実行できます。
相続人以外の親族が請求できる「特別寄与料」
2019年7月の民法改正により、相続人以外の親族が、被相続人に対して無償で療養看護や生活の面倒を見るなど「その他の労務の提供」を行った場合、または被相続人の財産維持、または増加について特別の寄与をしたと認められる場合には、その親族は相続人に対して「特別寄与料」の支払いを請求することができるようになりました。
親の相続が発生した場合、親の面倒を見ていた家族とそうでない家族とでは財産形成に対する貢献度合いが異なるため、単純に法定相続分で割りきれない場合も少なくありません。
そのため民法では、「寄与分」という区分により、被相続人の財産形成に寄与した相続人に対して、相続財産の上乗せを認めています。
ところが、「被相続人へ介護を行なうことによる寄与分」の場合は、時間を消費し、親の財産を取り崩しながら身をすり減らして介護をしたとしても、親の死後に他の相続人から「親に扶養されていたくせに!」と主張されることもあります。
ましてや、法定相続人ではない「子の配偶者」の立場である場合はなおさら、自分たちの貢献度合いを相続人たちに理解させるのは至難の業でした。
民法改正で「特別寄与料」の支払いを請求することができるようになったことで、義理の両親を介護してきた方の苦労が報われる可能性が高まったといえます。