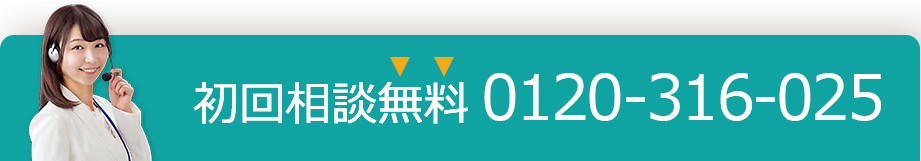認知症で判断能力を失う前に対策を
厚労省の「令和3年度簡易生命表」によれば、日本人の平均寿命は男性が81歳、女性が87歳と、いずれも過去最高となりました。65歳以上の人口は、総人口の28.4%。3.5人に1人が高齢者となっています(平成31年9月現在)。さらに、2025年には、認知症患者が700万人を超えると推計。これは高齢者の5人に1人が認知症になるという計算になります。
誰もが不安な認知症。認知症になる前にできる対策を紹介します。
認知症になるとどんな影響がある?
認知症になると、自分のお金を口座から引き出すことが簡単にはできなくなるだけでなく、株式の運用や不動産の処分なども難しくなります。
認知症になる前の対策としては、十分に判断能力があるうちに遺言書などを作成して、自分の財産をだれに相続させるかを決めておくこと。また、任意後見制度を利用することも有効です。
認知症対策として考えておきたい「任意後見制度」とは
任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する人である任意後見人を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。
この制度には「法定後見」と「任意後見」という2つの形式があり、法定後見制度は、すでに認知症などになって財産管理や契約行為ができない場合、裁判所が後見人を決めて保護するものです。
任意後見制度のメリット
任意の自然人・法人を選べるので、自身が信頼できると判断した方を選任することができる。
任意後見制度のデメリット
選任した人に専門的な知識がなく、後見人となることが大きな負担となったり、任意後見監督人の判断次第で思うような資産運用ができなくなるケースもある。
任意後見制度 利用の流れ
①後見人に何をしてもらいたいのか、具体的な内容を公正証書の形にまとめる
内容としては、「長男に毎月5万円の生活費を渡す」「ひとりで生活できなくなったら自宅を売って施設に入る」など。お金の運用についても希望を反映できます。
任意後見契約の締結は、公証役場で公証人の立会のもとで行う必要があります。
契約日前に公証役場に文案を提出し、日程などの打ち合わせをするため、専門家に依頼して進める場合が一般的です。
②判断能力のあるうちに自ら後見人を選ぶ
後見人には自分の親族を選ぶことができるほか、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するケースもあります。
専門家に頼んだ場合の費用は契約により異なりますが、目安として、司法書士の場合は契約時に20万円、後見開始時に15万円、発効後の月々の報酬は3万円程度となります。
③財産管理や生活、看護・介護について契約する
任意後見制度は、「ライフプランに基づいた事項を盛り込める」のが特徴。裁判所がお金の使い道を厳しく見る法定後見制度に比べると、自由度が高い制度といえます。
④判断能力が低下したら、後見人が後見開始の手続きをする
実際に認知症になった際など、任意後見業務を開始する場合は、裁判所が後見人からの申し立てを受けて、監督人(任意後見監督人)を選任します。
監督人は、後見人が適切に財産管理をしているか、不正に手続きしていないかをチェックし、定期的に裁判所に報告します。監督人は本人が選ぶことができません。主に弁護士・司法書士などの専門職が行う場合が多く、契約者本人の財産から報酬を支出することになります。(報酬は、目安として月1万円〜)
任意後見制度が利用されるケース
①障害のある子を持つ親が認知症対策のために利用するケース
親の認知症が進行していった場合、親が自分の財産を管理・処分できなくなってしまう可能性があります。
障害のある子と親が生計をともにしていた場合、一緒に生活が立ち行かなくなってしまう恐れがあるため、親の判断能力があるうちに、任意後見制度を契約するケースが少なくありません。
日常生活に必要な財産の管理・処分ができなくなった場合に備えるのが、この任意後見契約の役割と言えます。
②障害者本人が利用するケース
精神障害を持つ方が、元気なうちに自身の後見人を選任する場合があります。また、障害のある子どもが未成年のうちであれば、親権に基づいて両親が子どものための任意後見契約を締結することも可能です。